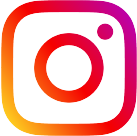山本左近NEWS No69
2025.10.1
総裁選の真っ只中ですが、9月29日、9月の月例経済報告が公表されました。月例経済報告は、『政府が毎月発表する日本経済の現状と見通しを示す公式な報告書』です。日米の関税交渉の影響などが気になるところですので、今回はこの内容を解説していきます。
〈景気に対する政府の評価〉
月例経済報告の冒頭には、政府の景気に対する総合評価が示されます。この9月は「景気は、米国の通商政策による影響が自動車産業を中心にみられるものの、緩やかに回復している。」とされていますので、景気は回復傾向であるというのが政府の判断であることがわかります。
〈日米関税交渉合意の影響〉
7月の関税交渉合意に伴い、企業の景況感は4~6月期を底に7~9月期以降、改善しています。
特に自動車産業では、交渉合意前の調査結果を大きく上回る景況感になっています。中小企業へのアンケートでも、交渉合意の前後で関税の「影響がある」あるいは「今後見込まれる」とする回答割合が減少。影響が「特にない」の割合も増加しています。
豊橋・田原に住む私たちの目線から見ても、自動車関連産業は、地域の雇用を支え、暮らしの中心となるものです。関税や為替リスクに備えつつ、電動化や合成燃料、リサイクル材といった新しい分野へ挑戦していくことが重要であると考えられます。
〈家計部門〉
家計部門では明るい材料も。7月の実質賃金は、夏季のボーナス増の影響により前年同月比でプラスに転じました。最低賃金も大きな変化があり、全国加重平均で1,121円と過去最大の引上げ。全都道府県で時給1,000円を超えたのは初めてです。若年層や子育て世代にとって、賃上げは働き方の選択肢を広げ、暮らしを安定させる好機となります。
最低賃金の上昇は、確かに企業にコスト増の懸念をもたらします。生産性の向上や業務効率化、高付加価値商品の開発、人材定着の促進など、賃上げをコストではなく投資と捉え、企業の力を強めることに活かすことが望まれます。
他方で、公定価格で決められている医療・介護福祉・保育・教育などはインフレ対応型の報酬改定がなくては、物価高や賃上げに対応できません。
〈輸出・生産〉
輸出や生産には停滞感が漂います。米国向け乗用車は今年前半の増加分の反動もあり、減少に転じました。国内生産も6月以降低下傾向にあります。企業収益は全体として高水準を維持していますが、4~6月期の製造業利益は前年同期比で減少しました。
〈株式市場の動き〉
株式市場では歴史的な動きがありました。日経平均株価は9月下旬に4万5000円を突破し、過去最高値を更新。株価の上昇は、一般的に企業業績の改善や経済の先行きに対する期待感を示します。バブル期のピークを大きく超えたこの水準は、日本経済に対する期待と信頼の高まりを示すものでもあります。
地元を回るなかでは「物価高によって生活が苦しい」というお声を多くうかがいます。株価の上昇が賃上げに直結するわけではありませんが、賃上げの余地は拡大します。現在の株価上昇を追い風にして、物価高を上回る実質賃金の上昇が進むこと、また早急かつ大胆な物価高対策が日本経済の真の再生に繋がるものと考えています。